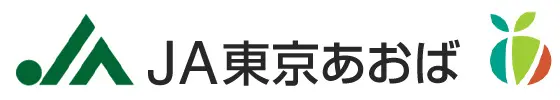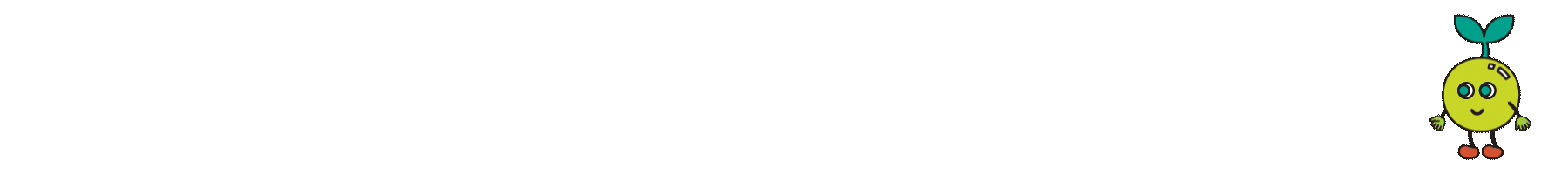各組織の活動

板橋区民まつりで植木市開催
板橋地区園芸部会は10月18日(土)・19日(日)の2日間、板橋区・板橋区観光協会主催の「第54回板橋区民まつり」に植木市を出店しました。園芸農家らが100種類以上の観葉植物・花・球根などを販売し、多くの来場者で賑わいました。
植木市は都市農業のPRと地場産の良質な植木や花を地域の人々に提供することが目的。生産者に直接、育て方のコツを聞ける機会でもあり、毎年楽しみにしているリピーターもたくさん来場していました。
毎年人気のチューリップ球根詰め放題に挑戦していた子どもは「植木市で詰め放題に挑戦できるとは思いませんでした。袋いっぱいの球根をちゃんと育ててみたい」と嬉しそうに話しました。
販売に参加した部会員は「天候にも恵まれ、しっかりとPR・販売ができました。近年は観葉植物が人気で、若い客層も増えているので、今後も喜ばれる花や植木を作っていきたい」と話しました。

共生の会茶話会 ミニデイサービスを開催
共生の会茶話会は10月14日(火)、ミニデイサービスを開催しました。この催しは75歳以上を対象とし、36人の参加者が集まりました。
当日は多肉植物の寄せ植え講習会を行い、昼食には会員や女性部役員によるすずしろ汁や田舎まんじゅうを作りもてなしました。その後のカラオケ大会では皆さんの元気な歌声を披露し、ビンゴゲームなども、大いに盛り上がりをみせました。
同会の高橋康代会長は「多くの参加者が集まり、元気に楽しんでもらえてよかった。今後も楽しい会を開催していきたい」と話しました。

よさこいサークルすずしろ「第26回東京よさこい」に参加
よさこいサークルすずしろは、10月12日(日)、豊島区池袋を中心に開催する「踊りの祭典 第26回東京よさこい」に出場しました。同会は今年で結成10周年を迎え、農業をテーマとしたよさこい「笑顔花(えがおばな)」を20人で披露しました。
大塚会場ではトップバッターを務め、男性メンバーによる掛け声に合わせ、多くの応援団や観客の前で元気よくスタートしました。その他に、巣鴨駅前、池袋みずき通り、アゼリア通りの4か所で踊りを披露しました。
大トリとなったアゼリア通りでは、「笑顔花」を作詞作曲した松田栄作さんによる生歌で踊り、会場は最高の盛り上がりとなりました。
同サークルの加藤千鶴子部長は「すずしろを結成し10周年を迎え、皆さんの応援のおかげで大舞台でも披露できるようになり、感謝しかありません。これからも若い世代に繋がるように、私たちも楽しんでいきたい」と話しました。

秋の植木市盛況
板橋地区園芸部会は10月10日(金)から3日間、板橋区主催の「秋の植木市」に出店しました。イベントは40年以上続く区の恒例行事。会場の高島平噴水緑地広場には、色鮮やかな植木や花が並びました。植木市は都市農業のPRと地場産の良質な植木や花を地域の人々に提供することが目的。毎年植木市で植木やお花を購入しているという来場者が多く、生産者に相談をしながら購入する姿が印象的でした。
花を購入した来場者からは「毎年、良質な花を買えて嬉しい。去年買ったお花もまだ咲いています。今回も楽しみながら育てたい」と笑顔で話しました。
販売に参加した部会員は「3日間、しっかりと都市農業のPRと販売ができました。毎回、来場してくれることに感謝しています。リピーターを増やしていくためにも、もっと喜ばれる植木や花を育てていきたい」と話しました。

城北ぶどう研究会 ブドウ食味検討会実施
城北ぶどう研究会は8月19日(火)、練馬春日町支店で食味検討会を実施しました。練馬区でブドウを栽培する10名の生産者が「高尾」「藤稔」「シャインマスカット」など14品種28点を持ち寄りました。重量や糖度、色合いなど5項目に基づき測定し、試食して違いを比べました。
検討会には会員のほか、区部農業改良センターの普及員、練馬区都市農業課の職員が参加しました。
普及員は「6月の高温や7月の少雨等、今年も厳しい環境であったが、本日測定したものは糖度も高く、着色もよい品質のよいものでした」と講評しました。
ブドウは8月から9月中旬にかけて、管内の庭先販売所やJA直売所で販売され、贈答用として人気があります。

夏季合同講習会開催
練馬地区資産管理部会は8月5日(火)、子会社である東京協同サービス株式会社オーナー会(T・O会)と合同で夏季講習会を開きました。今年度より第10次中期経営計画(農業振興計画含む)を実践しており、これらの勉強会は「組織基盤の活性化」に該当。当JAの顧問税理士よる「令和7年度税制改正ポイント」をわかりやすく、会員に説明しました。
参加者は「資産管理と税制は切っても切れない関係。今回の税制ポイントをわかりやすく説明を受け、助かりました」と話しました。
資産管理部渡部勝部長は「今回のセミナーも多くの会員が参加してくれて感謝しています。今後も会員のためになるセミナーを開催していきたい」と話しました。

大泉新鮮直売組合 区役所マルシェ開催
大泉新鮮直売組合が7月28日(月)に練馬区役所本庁舎1階アトリウムで「区役所マルシェ」を開きました。。組合員4名が、夏野菜を中心に、地場産農産物を使用した加工品も販売しました。農家が自ら栽培した地場産農産物の販売をすることで、多くの区民に地元で栽培された農産物の魅力を伝え、直売所に来店してもらえるようアピールする狙いもあります。
同組合の莊光男組合長は「来店者と対話し、地場産農産物の魅力を伝えることができました。今後も、マルシェを通じて地元の農業を盛り上げていきたい」と話しました。

石神井地区共生の会 ミニデイサービスお楽しみ会を開催
石神井地区共生の会は6月26日(木)、石神井支店でミニデイサービスお楽しみ会を開き、70歳以上の組合員28人が参加しました。椅子に座ったままボールなどを使い、楽しく体を動かす「生きがい体操」やチームに分かれて対戦する「輪投げ」などのレクリエーションを通じ、参加者同士での親睦を深めました。また、昼食は同会会員が手作りしたみそ汁やデザートで参加者をもてなしました。
同会の八方博子代表は「参加者に楽しんでもらえるよう、会員の中でたくさん意見交換をしながら準備を進めてきました。今回も参加者の元気な姿や笑顔を見ることができてよかった」と話しました。
JAでは組合員の生活支援の一環としてミニデイなど催しの支援を今後も引き続き行っていく。

柿高品質に 摘蕾講習会実施
練馬地区果樹園芸部会は5月9日(金)、同部員の畑を会場に柿の摘蕾(てきらい)講習会を開き、部員ら8人が参加しました。今年2月にも同会場で剪定講習会を開いており、今回は剪定した樹木の樹形や蕾の付き具合なども確認しました。
講師は前回に引き続き、大泉地区の生産者で東京都指導農業士の資格を持つ荘埜晃一氏と、都区部農業改良普及センター城北分室の職員が務めました。
荘埜氏からは、摘蕾を早い時期に行うことは、大きな実を育てるだけでなく、作業の効率化・省力化につながるなどの説明があった。説明後には実際に参加者全員で摘蕾の作業も行いました。
宮本正裕部会長は「省力化を図りながらも品質の良い果樹栽培に努めていきたい」と話しました。

春の訪れ告げる 植木市にぎわう
板橋地区園芸部会は4月18日(金)から20日(日)の3日間、板橋区主催の「春の植木市」に参加しました。イベントは40年以上続く区の恒例行事。会場の高島平噴水緑地広場には、春を彩る植木や草花、野菜苗などが並び、訪れた多くの人が楽しみながら買い求めました。
植木市は都市農業のPRと地場産の良質な植木や花を地域の人々に提供することが目的。植木を購入した来場者からは「毎年、楽しみにしていて、プロの生産者からアドバイスを頂いてしっかりと育てたい」と笑顔で話しました。
販売に参加した部会員は「3日間多くの来場者でにぎわいました。近年、暑さや資材高騰の影響もあり植木や花の生育も大変だが、来場者の笑顔を見ると頑張って良かったです。来月も頑張って植木市を盛り上げたい」と話しました。
春の植木市、次回は5月9日(金)から11日(日)に同会場で行う予定です。